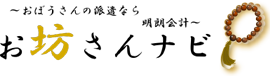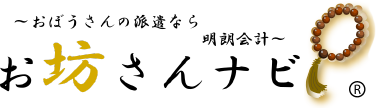寒さが厳しくなり、季節はすっかり冬ですね。
今年もあとわずかとなりました。
皆さまにとって、どのような1年でしたでしょうか。
ところで12月といえばお正月に飾る鏡餅を準備する月でもあります。
この鏡餅どうして飾るかご存じでしょうか?
鏡餅や門松、注連縄などのお正月飾りは、「年神様」を迎えるためのもので、新しい年に豊かな実りをもたらしてくれる神様がいらっしゃるという、古くからの信仰に基づくものだそうです。
つまり、お迎えする年神様の依り代、神様の居場所となるのが「鏡餅」なのです。
だから、銅鏡のように丸いそうです。
また、年神様は、私たちに新しい年に豊かな実り(幸福)をもたらしてくれると共に「魂(生きる力)」を分けてくださると考えられています。
年神様の「魂」が宿った鏡餅の餅玉をお雑煮などで食べることで「生きる力」を分けてもらうという意味合いもあるそうです。
ちなみに、その年の魂(=餅玉)を家長が家族に分け与えた「御年魂」というのが、
お年玉のルーツです。現在はお金に変わってしまいましたが、鏡餅をお雑煮やぜんざいにして食べるのは、その名残だそうです。
この鏡餅、飾る日は12月28日や30日が一般的です。
29日は「二重苦」「苦持ち」「苦をつく」と言って、「九」が「苦」に通ずることから縁起が悪いとされているからです。
場所によっては、29日は「ふく=福」をもたらすと解釈するところもあるようです。
また、31日は一夜餅と言い、縁起が悪いと避けられています。
一年の終わりに大掃除をし、家の中で大切だと思っている場所、リビングや玄関に鏡餅を置いて新年を迎えられてはいかがでしょうか?
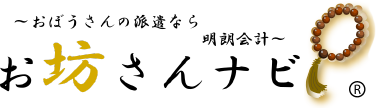
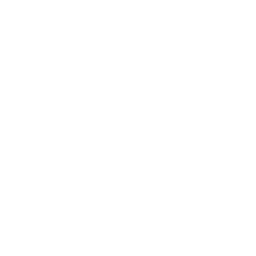 お問合せはこちら
お問合せはこちら